「戸籍 謄本 コンビニでのやり方・セブンイレブン」と検索してこのページにたどり着いた方は、おそらく役所に行く時間がなく、コンビニで手軽に戸籍謄本を取得できないかお悩みではないでしょうか。
結論から言えば、セブン‐イレブンでは戸籍謄本の取得が可能です。
ただし、誰でもいつでも発行できるわけではありません。取得にはマイナンバーカードや利用者証明用電子証明書が必要で、いくつかの注意点や制限があることを理解しておくことが大切です。
本記事では、「セブンイレブンで戸籍謄本は取れますか?」という基本的な疑問から、「戸籍謄本を取る際に本籍地が違う場合」の対応方法、そして「スマホ用電子証明書でも戸籍謄本は取れる?」という新しい取得手段についても詳しく解説します。
加えて、「コンビニで戸籍謄本が取れない原因とは?」「戸籍謄本の料金はいくら?」「印刷できる店舗や機種の確認方法」「即日発行は可能?何日かかる?」など、知っておきたい情報を網羅的にまとめています。
さらに、「住民票や印鑑証明書の取得も可能?」など、戸籍以外の証明書についても触れているので、ぜひ最後まで読み進めてください。コンビニ交付を失敗なくスムーズに行いたい方に向けた、実用的なガイドです。
<記事のポイント>
・セブン‐イレブンで戸籍謄本を取得するための手順
・コンビニで戸籍謄本が取れない原因とその対処法
・マイナンバーカードや電子証明書の必要性と注意点
・本籍地が異なる場合の対応方法や事前申請の流れ
戸籍謄本をコンビニで取る・やり方【セブンイレブンの場合】
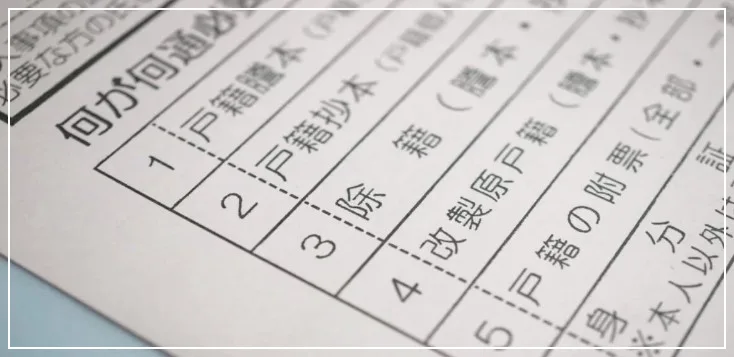
- セブン‐イレブンで戸籍謄本は取れますか?
- 戸籍謄本がコンビニで取れない原因とは?
- マイナンバーカードが必要な理由とは?
- 戸籍謄本取る際に本籍地が違う場合
- セブンイレブンで戸籍謄本を取るための操作手順
- スマホ用電子証明書でも戸籍謄本は取れる?
セブン‐イレブンで戸籍謄本は取れますか?
セブン‐イレブンでは、戸籍謄本を含む各種証明書を取得することができます。ただし、誰でもいつでも利用できるわけではありません。
まず大前提として、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていて、かつ利用者証明用電子証明書が有効である必要があります。さらに、対象者の「本籍地」と「住民登録地」によっては、事前の利用登録申請が必要となる場合もあります。
証明書の取得は、店舗に設置されたマルチコピー機(キオスク端末)を使って行います。
端末のメニューから「行政サービス」を選択し、指示に従ってマイナンバーカードを読み取らせた後、戸籍謄本の発行が可能です。このとき、事前に設定した暗証番号(4桁)を入力して本人確認を行う必要があります。
なお、戸籍謄本の発行ができる時間帯は限られており、基本的には平日9時から17時の間と定められている自治体が多いです。住民票のように早朝や深夜にも取得できるわけではないため、時間を誤ると利用できない点に注意が必要です。
また、戸籍謄本の交付ができるのは「本籍地の自治体がコンビニ交付に対応している場合」に限られます。すべての市区町村が対応しているわけではないため、事前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)のサイトなどで対応状況を確認しておくと安心です。
つまり、セブン‐イレブンで戸籍謄本を取ることは可能ですが、「マイナンバーカードの保有」「本籍地の自治体の対応」「利用時間帯の把握」といった複数の条件が揃っていることが前提になります。
条件を満たしていれば、役所に行かずに証明書を取得できる非常に便利なサービスといえるでしょう。
戸籍謄本がコンビニで取れない原因とは?
戸籍謄本がコンビニで取得できない場合、いくつかの明確な原因があります。
まず最も多いのは、対象者の「本籍地の自治体がコンビニ交付サービスに対応していない」ことです。現在、多くの市区町村がこのサービスに参加していますが、すべてではありません。
そのため、自分の本籍がある自治体がサービス対象外であれば、そもそも戸籍謄本をコンビニで取得することはできません。
次に、マイナンバーカードが無効または未発行の場合も原因になります。このサービスでは、必ず利用者本人のマイナンバーカードが必要であり、さらにカード内の「利用者証明用電子証明書」が有効であることが条件です。
戸籍謄本がコンビニで取得できない主な原因と対処の目安
| 原因 | 内容 | 対処法・確認ポイント |
|---|---|---|
| 本籍地自治体が非対応 | 自分の本籍地がコンビニ交付に参加していない | 自治体の公式サイトまたは「J-LIS」の対応市区町村一覧で確認 |
| マイナンバーカード未所持・無効 | カードが発行되어 있지ない、または有効期限切れ・ロック | 市区町村窓口で発行または暗証番号の初期化手続き |
| 利用者証明用電子証明書の不備 | ICチップ内の証明書が失効または未搭載 | マイナンバーカードの設定内容を役所で確認 |
| コンビニ発行時間外の利用 | 戸籍謄本は原則「平日9時〜17時」のみ発行可 | 利用時間内(平日昼間)に再度アクセス |
| 利用登録申請が未完了 | 住民票の住所と本籍地が異なる場合に初回申請が必要 | 事前に役所で利用登録申請を行う |
| 機種依存文字の使用 | 戸籍に機種依存文字(旧字や外字)が含まれる場合 | 役所の窓口で直接取得を検討 |
| 自治体システムの一時停止 | メンテナンス中・システム障害の場合 | 自治体の告知情報を確認後、再試行 |
もし暗証番号を3回間違えてロックがかかっている場合や、有効期限が切れている場合には、端末からの認証ができず取得ができません。
また、コンビニでの発行時間外に操作していることも理由のひとつです。住民票など一部の証明書は早朝から深夜まで発行可能ですが、戸籍謄本の場合、平日9時〜17時に限定されていることが一般的です。
週末や夜間は対応していないため、知らずにアクセスしても「現在この証明書は発行できません」と表示されることがあります。
加えて、住民票や本籍が一致していない場合、初回に限り「利用登録申請」が必要となるケースもあります。この申請を事前に済ませていないと、戸籍謄本の交付手続きには進めません。
さらに、戸籍に記載されている文字が機種依存文字である場合も、コンビニでの交付が制限されることがあります。
これらのように、取得できない原因は複数あり、利用者側にとっても把握が難しい点があるかもしれません。したがって、事前に自治体の公式ページやJ-LISなどで確認を行い、必要な準備を整えてから利用することが大切です。
マイナンバーカードが必要な理由とは?
コンビニで戸籍謄本を取得する際に、マイナンバーカードが必要なのは、本人確認とセキュリティ確保のためです。
具体的には、カード内に搭載された「利用者証明用電子証明書」を使って、証明書発行端末での本人確認が自動的に行われる仕組みになっています。この電子証明書は、4桁の暗証番号と連動しており、他人によるなりすましや不正取得を防ぐ重要な役割を担っています。
以前は住民基本台帳カード(住基カード)も一部で利用されていましたが、現在ではマイナンバーカードへの移行が完了しており、新規発行や対応は停止されています。そのため、証明書の自動交付サービスを利用するには、マイナンバーカードが実質的に唯一の方法となっています。
一方で、マイナンバーカードを持っていても、利用者証明用電子証明書が設定されていない場合は利用できません。これはカード発行時に「不要」と設定した方に多く見られます。もし利用したい場合には、自治体の窓口で再設定手続きを行う必要があります。
さらに、セブン‐イレブンなどの店舗では、マイナンバーカードを読み取ってから各種証明書の発行を進める構成となっており、カードなしでは端末操作が進行できません。
また、スマートフォンに電子証明書を搭載するJPKI方式も一部対応していますが、現時点では機種や設定に制限があるため、基本的には物理カードを持参するのが確実です。
このように、マイナンバーカードは本人確認と安全な情報の取り扱いを両立するための鍵であり、コンビニ交付サービスの利用においては必須アイテムといえるでしょう。取得を希望される方は、早めに申請を済ませておくことをおすすめします。
戸籍謄本取る際に本籍地が違う場合

戸籍謄本をコンビニで取得しようとした際、「本籍地が現在の住民票のある場所と異なる」というケースは少なくありません。このような場合でも、セブン‐イレブンなどのコンビニを利用して戸籍謄本を取得することは可能です。
ただし、一定の条件と手続きを満たす必要があります。
まず確認すべきなのは、自分の本籍地にある市区町村が「戸籍証明書のコンビニ交付サービス」に対応しているかどうかです。もし対応していない場合、そもそもコンビニでの取得はできません。その場合は、役所窓口や郵送などの別の方法を選ぶ必要があります。
次に必要となるのが、「本籍地の利用登録申請」です。
この申請は、住民登録地と本籍地が異なる方が、初めてコンビニで戸籍謄本を取得する際に行うものです。
申請の方法は主に2つあります。ひとつはコンビニのマルチコピー機から直接申請する方法で、もうひとつは自宅のパソコンにICカードリーダーを接続してオンラインで申請する方法です。
申請時には、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。さらに、申請から利用可能になるまでに数日(通常は5営業日以内)かかるため、急ぎで証明書が必要な場合は注意が必要です。利用登録が完了すると、以後は登録なしでスムーズに取得できるようになります。
なお、登録が完了しても、証明書の交付には時間制限があります。ほとんどの自治体では平日9時〜17時に限定されていますので、発行の際には時間にも留意してください。
このように、本籍地が異なる場合でも一度手続きを行えば、次回からは全国の対応店舗でスムーズに証明書を取得できます。忙しい方や遠方の本籍地に行けない方にとって、大変便利な仕組みです。
セブンイレブンで戸籍謄本を取るための操作手順
セブンイレブンで戸籍謄本を取得するには、マルチコピー機を操作して手続きを進める必要があります。初めての方でも戸惑わずに利用できるよう、順を追って丁寧に解説します。
まず、店舗内に設置されているマルチコピー機の前に立ち、画面に表示される「行政サービス」のボタンをタッチします。このメニューから「証明書交付サービス」を選択することで、戸籍謄本などの取得に進むことができます。
続いて、マイナンバーカードをカード読み取り部分に置いて、本人認証を行います。この際に、事前に設定した「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)を入力する必要があります。
間違えるとロックされるため、注意が必要です。認証が完了したら、画面の指示に従って「戸籍証明書」を選択し、証明書の種類を「全部事項証明書」または「個人事項証明書」から選びます。
その後、必要な部数を入力し、内容を最終確認します。訂正が必要な場合は、戻って選び直すこともできます。
確認が終わったら、料金をコインベンダーに投入し支払いを済ませると、マルチコピー機から証明書が印刷されます。取り忘れを防止する音声案内が流れるため、印刷完了後は速やかに証明書とマイナンバーカードを回収してください。
セブンイレブンで戸籍謄本を取得する手順と各工程のポイント
| 手順 | 内容 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ① マルチコピー機の起動 | 店内のマルチコピー機の前に立ち、「行政サービス」をタッチ | 証明書交付メニューはトップ画面から選択可能 |
| ② 証明書交付サービス選択 | 「証明書交付サービス」→「戸籍証明書」選択 | 表示案内に沿って進むことでスムーズに操作可 |
| ③ マイナンバーカード読み取り | 所定の位置にマイナンバーカードを置く | カード裏面のICチップ部分が読み取り対象 |
| ④ 暗証番号の入力 | 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力 | 3回間違えるとロックされるため慎重に入力 |
| ⑤ 証明書の種類選択 | 「全部事項証明書」または「個人事項証明書」を選択 | 用途に応じて適切な種類を選ぶ必要あり |
| ⑥ 必要部数入力・内容確認 | 枚数を指定し、画面の内容を確認 | 誤入力があれば戻って修正可能 |
| ⑦ 料金支払い | コインベンダーに現金を投入し支払いを完了 | 紙幣は利用不可の機種もあるため小銭推奨 |
| ⑧ 印刷・受け取り | 印刷が開始され、証明書が出力される | マイナンバーカードと証明書の取り忘れに注意 |
操作自体は10分程度で完了することが多く、役所に行かずに手続きができる便利な方法です。ただし、自治体や本籍地によっては事前に「利用登録申請」が必要な場合があるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
スマホ用電子証明書でも戸籍謄本は取れる?
スマホ用電子証明書を使って戸籍謄本を取得できるかどうかは、利用する自治体と機種の対応状況に左右されます。
現在、総務省およびデジタル庁が提供するサービスの一環として、一部のAndroid端末やiPhoneに電子証明書を搭載し、スマートフォンだけで証明書交付を行う取り組みが始まっています。
スマホをマイナンバーカード代わりに使えるこの仕組みは、2023年末から順次導入され、対応機種も拡大中です。
しかし、すべての自治体が戸籍証明書に対してスマホ用電子証明書を対応させているわけではありません。例えば、江戸川区など一部自治体では、スマホ用電子証明書による戸籍謄本の取得は「非対応」とされています。
したがって、スマートフォンを使って戸籍謄本を取得したい場合は、まず自治体の公式サイトやJ-LISで対応状況を確認する必要があります。
また、スマホ用電子証明書を利用するには、あらかじめアプリのインストールや本人確認、暗証番号の設定などが求められます。これらの準備が整っていないと、店頭での手続きができません。
さらに、スマホとマルチコピー機との接続性やNFC(近距離無線通信)対応など、技術的な制約もあるため、確実性を求める場合は物理的なマイナンバーカードの利用が現時点ではより安心です。
つまり、スマホ用電子証明書で戸籍謄本を取得することは可能な場合もありますが、利用可能かどうかは市区町村によって異なります。今後の対応範囲の拡大が期待されるものの、利用前には必ず確認を行うべきです。
セブンイレブンで戸籍謄本を取る際のやり方は?【コンビニならではの利点】
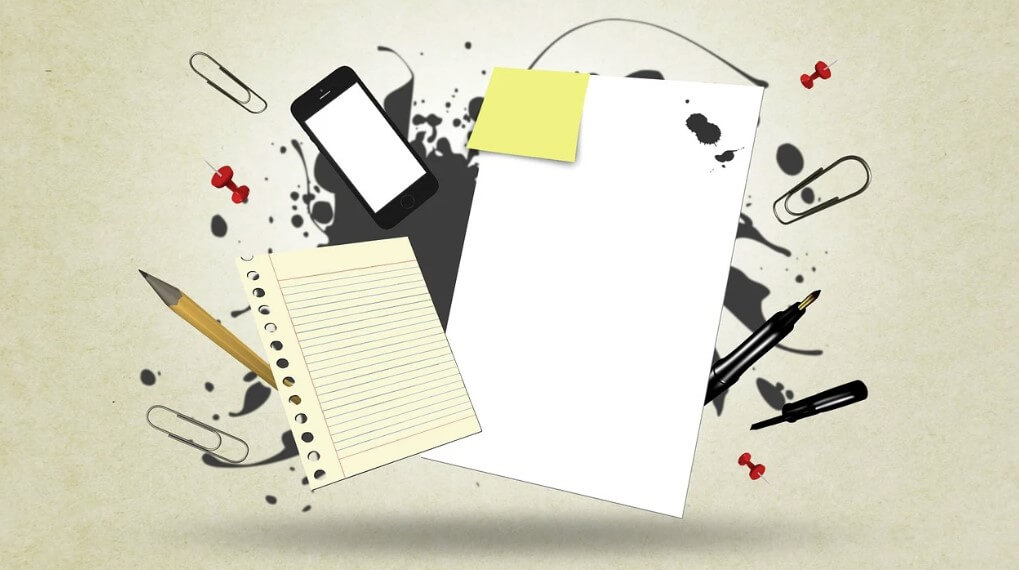
- 戸籍謄本の取得可能な時間帯と曜日
- 戸籍謄本の料金はいくら?セブンイレブンの場合
- 戸籍謄本が印刷できる店舗と設置機種の確認方法
- 住民票や印鑑証明書の取得も可能?
- コンビニ交付で取得できないケースと対処法
- 戸籍謄本をコンビニで取る場合何日かかる?即日発行できるの?
戸籍謄本の取得可能な時間帯と曜日
戸籍謄本をコンビニで取得できる時間帯は、住民票など他の証明書とは異なり、制限が設けられている場合が多いです。
例えば、多くの自治体では戸籍関係の証明書は平日の「午前9時から午後5時」までと設定されており、それ以外の時間帯ではマルチコピー機を操作しても戸籍謄本のメニュー自体が表示されないことがあります。
一方、住民票や印鑑登録証明書などは、朝6時半から夜11時まで取得可能な自治体が大半であり、年末年始やシステムメンテナンス時を除いてほぼ毎日利用できるのが一般的です。これと比較すると、戸籍謄本の取得可能時間は短く、限定されていることが分かります。
この違いの背景には、戸籍情報の管理がより慎重に取り扱われるべき性質であること、システムが連携している自治体同士での確認作業に時間を要することなどが関係しています。
また、土日祝日に関しては、戸籍証明書のコンビニ交付自体を停止している自治体も多いため、注意が必要です。
なお、自治体によっては一部例外も存在し、例えばメンテナンス時間を避ければ夜間の発行が可能というケースもありますが、これはごく限られた事例です。そのため、利用予定の自治体公式サイトを事前に確認し、取りに行く時間帯を誤らないようにすることが大切です。
つまり、戸籍謄本はいつでもコンビニで取得できるわけではありません。時間帯と曜日を把握してから行動することで、無駄足を防ぎ、スムーズに証明書を受け取ることができます。
戸籍謄本の料金はいくら?セブンイレブンの場合
戸籍謄本の料金は自治体によって異なりますが、セブンイレブンなどのコンビニで取得する際には、1通あたり350円程度が一般的な目安です。
たとえば江戸川区や静岡市などでは、「戸籍全部事項証明書」または「戸籍個人事項証明書」の交付手数料がそれぞれ1通350円と定められています。
この金額は市区町村の窓口で取得する場合とほぼ同じか、少し安いケースもあります。中には、2025年度以降、窓口よりも100円安く設定している自治体もあり、コンビニ交付を推奨する動きが見られます。
ただし、免除対象となる人(生活保護受給者や災害被災者など)であっても、コンビニで取得した場合は手数料が発生する点に注意が必要です。免除を希望する場合は、窓口での申請が必要です。
セブンイレブンなどのコンビニで戸籍謄本を取得する際の料金・支払い・注意点
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 【料金】1通あたりの目安 | 350円程度 | 多くの自治体(例:江戸川区・静岡市など)で統一料金 |
| 窓口との料金比較 | 同等または一部自治体ではコンビニの方が100円安い | 2025年度以降、コンビニ交付を推奨する自治体も |
| 免除制度の適用可否 | コンビニ交付では免除不可 | 生活保護・災害被災者は役所窓口で申請が必要 |
| 支払い方法 | 現金・電子マネー(nanaco)対応が一般的 | クレジットカード・QRコード決済は非対応の端末が多い |
| 間違えた証明書の料金 | 返金不可 | 例:個人事項証明書と全部事項証明書を取り違えた場合も有料 |
| お得に使う方法 | 自治体の料金比較+nanaco支払いでポイント付与活用も | nanacoチャージも事前に済ませておくとスムーズ |
支払い方法については、現金または電子マネー「nanaco」が利用できる店舗が多く、券売機のように使いやすい仕様となっています。ただし、クレジットカードやQRコード決済には対応していない端末もあるため、利用前に準備しておくと安心です。
さらに、間違って取得してしまった証明書の料金は返金不可です。たとえば、「全部事項証明書」と「個人事項証明書」を誤って選択した場合でも、取り消しや交換はできません。こうした点からも、操作前の確認が重要です。
つまり、セブンイレブンでの戸籍謄本の料金はおおよそ350円で、利便性を考えれば高くはありません。しかし、注意点を理解せずに利用すると手数料が無駄になってしまうこともあるため、正しい手順と情報を事前に押さえておくことが肝心です。
戸籍謄本が印刷できる店舗と設置機種の確認方法
コンビニで戸籍謄本を取得する際、すべての店舗で利用できるわけではありません。対象となるのは、マルチコピー機(キオスク端末)が設置されており、かつ行政サービスに対応している店舗に限られます。
全国展開しているセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオン系列などが主な対象ですが、各店舗によって設置状況は異なるため、事前確認が欠かせません。
確認方法として最も確実なのは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供する「コンビニ交付対応店舗検索」ページを利用することです。
このサイトでは、対応している市区町村と、それに基づく利用可能な証明書、利用時間、設置店舗情報などが一括で確認できます。また、各自治体の公式サイトにも、区内で利用できる店舗名や住所が掲載されているケースが多く、ここでも信頼性の高い情報が得られます。
次に、設置されているマルチコピー機が対応機種かどうかを確認することも大切です。例えば、セブン‐イレブンでは富士フイルム製のマルチコピー機が使われており、証明書発行機能が標準装備されています。
ただし、一部の店舗では機種が古く、証明書交付機能が未対応である場合もあります。現地で確認する際は、「行政サービス」や「証明書交付サービス」ボタンが表示されるかどうかを目安にしましょう。
このように、確実に戸籍謄本を印刷できる店舗を見つけるためには、ネットでの事前確認と現地での端末チェックが欠かせません。証明書の取得をスムーズに進めるためにも、事前準備を怠らないことが成功のカギです。
住民票や印鑑証明書の取得も可能?

戸籍謄本に加えて、住民票の写しや印鑑登録証明書もコンビニで取得することができます。
これらの証明書は、戸籍証明書よりも取得可能な時間が広く、平日・土日祝を問わず、朝6時30分から夜11時まで利用可能な自治体が多いのが特徴です。
年末年始(12月29日~1月3日)や定期メンテナンスの時間帯を除けば、ほぼ毎日発行できる利便性が大きな魅力となっています。
住民票の写しについては、世帯全員が記載された「謄本」と、本人のみや一部の家族だけを記載した「抄本」のどちらも選択可能です。
印鑑登録証明書については、事前に市区町村で印鑑登録を済ませていることが条件で、登録済みであればマイナンバーカードを使って簡単に取得できます。ただし、カード発行時に「利用者証明用電子証明書」を不要としていた場合は、あらかじめ役所で再設定が必要になります。
なお、セブン‐イレブンやファミリーマートなどのマルチコピー機において、画面に「行政サービス」や「証明書交付」メニューが表示されない場合、その店舗ではサービスを利用できません。
設置店舗と時間帯が合っていても、機種が非対応である可能性があるため注意が必要です。
このように、住民票や印鑑登録証明書も非常に手軽に取得できる手段としてコンビニ交付は広く活用されています。日中に役所へ行けない方にとって、大きな助けになるサービスです。
コンビニ交付で取得できないケースと対処法
コンビニ交付は非常に便利なサービスですが、すべての状況で利用できるわけではありません。いくつかの取得不可ケースがあるため、それぞれの状況に応じた対処法を知っておく必要があります。
まず代表的な例として、マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」が搭載されていない場合があります。カード発行時に「不要」としてしまった場合は、再度役所で証明書を設定する手続きが必要です。
また、暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかり、これも解除のために役所や一部のセブン‐イレブンで初期化手続きを行う必要があります。
次に、本籍地が別の市区町村にある場合、その自治体が戸籍のコンビニ交付に対応していないと利用できません。この場合、窓口または郵送での請求が必要となります。
さらに、DVやストーカー行為などにより支援措置を受けている方は、安全上の観点からコンビニ交付が利用できない決まりになっています。このような場合は、直接窓口で対応することが求められます。
また、住民票コードや過去の住所情報、死亡者を含む情報を含めた住民票の写しなど、詳細な内容を含む証明書はコンビニ交付の対象外です。特殊な記載が必要な場合は、必ず窓口での申請が必要となります。
このように、すべての人がすべての証明書を取得できるわけではありませんが、対処方法を理解していれば慌てることなく対応できます。事前に自治体の対応状況や必要な準備を確認し、該当しないかをチェックしておくことが大切です。
戸籍謄本をコンビニで取る場合何日かかる?即日発行できるの?
戸籍謄本をコンビニで取得する場合、基本的にはその場で即日発行されます。
操作が完了すれば、マルチコピー機から数分以内に印刷され、すぐに持ち帰ることができる点が最大のメリットです。役所に行く時間がない方にとって、このスピード感は大きな魅力でしょう。
ただし、即日発行が可能なのは、いくつかの条件を満たしている場合に限られます。たとえば、本籍地が現在の居住地と同じ市区町村である場合、マイナンバーカードさえあれば事前申請なしで即時に取得できます。
一方で、本籍地が異なる市区町村にある場合は、事前に「利用登録申請」を済ませておく必要があります。この申請には数日~5営業日ほどかかることがあり、登録が完了しないと戸籍謄本の交付はできません。
さらに、戸籍の内容に変更があったばかりのとき(婚姻・出生・転籍など)は、システムに反映されるまでに時間がかかることもあります。この場合、内容が最新でない可能性があるため、急ぎで正確な情報が必要な場合には、窓口で直接取得する方が確実です。
また、利用時間にも注意が必要です。多くの自治体では戸籍証明書の交付は平日の午前9時~午後5時に限定されており、夜間や休日には発行できません。時間帯を誤ると即日発行どころか、端末操作自体ができないケースもあるため、事前の確認が大切です。
このように、条件が整えばコンビニで戸籍謄本は即日取得できますが、状況によっては日数がかかることもあります。スムーズに手続きするには、自身の状況に応じた準備と確認が欠かせません。
まとめ:戸籍謄本コンビニでのやり方・セブンイレブンで簡単に!

- セブンイレブンで戸籍謄本を取得するにはマイナンバーカードが必須
- マイナンバーカードには利用者証明用電子証明書が必要
- 操作はマルチコピー機の「行政サービス」から進める
- 暗証番号(4桁)の入力で本人確認を行う
- 発行できるのは本籍地がコンビニ交付に対応している自治体に限られる
- 発行時間は平日9時から17時に限定されている自治体が多い
- 初回のみ「利用登録申請」が必要なケースがある
- 申請はコンビニ端末またはパソコンで可能
- 申請完了までに最大で5営業日ほどかかる
- 住民票や印鑑証明書は平日・土日問わず取得可能な場合が多い
- スマホ用電子証明書での取得は一部自治体・機種のみ対応
- コンビニでの交付手数料は概ね1通350円前後
- 設置店舗や端末の対応状況はJ-LISサイトで確認可能
- 取得できない場合は原因に応じて再設定や窓口対応が必要
- 条件を満たせばその場で即日印刷・持ち帰りが可能
・2026年結婚式の良い日カレンダー!入籍日におすすめの日取り
・2026年最強開運日ランキング!縁起のいい日と過ごし方


コメント