2026年に向けて、所得税の扶養控除制度が大きく変わることをご存じでしょうか。
今回の税制改正では、私たちの手取り額に直結する重要な変更点がいくつも含まれています。扶養控除はどうなるのか、扶養控除はいくらになるのか、といった疑問から、扶養廃止はいつから?あるいは配偶者控除は廃止される?といった将来への不安まで、多くの方が気にされていることでしょう。
特に、年末調整で提出する申告書にも変更があるため、早めに情報を把握しておくことが大切です。この記事では、2026年扶養控除の改正内容を分かりやすく解説します。
<記事のポイント>
・令和7年分(2025年)の所得税から適用される制度変更の概要
・基礎控除と給与所得控除の引き上げによる「年収の壁」の変化
・新設される「特定親族特別控除」の対象者と控除額
・年末調整や申告書の様式変更と具体的な注意点
2026年扶養控除の改正内容を解説

- 結局、扶養控除はどうなるのか?
- 扶養控除はいくらになるのか解説
- 高校生年代の扶養廃止はいつから?
- 配偶者控除は廃止される?
- 特定親族特別控除の新設について
結局、扶養控除はどうなるのか?
2026年(令和8年)に向けて扶養控除制度自体がなくなるわけではありません。しかし、制度の内容は令和7年度税制改正によって大きく見直されることになります。
この改正の主な目的は、長年の課題であった「年収の壁」による働き控えを解消し、経済の活性化を促すことです。また、所得が低い層への支援を強化する狙いもあります。
具体的には、所得税を計算する上で基礎となる「基礎控除」や「給与所得控除」の金額が引き上げられます。これにより、税金の負担が軽減される人が多くなる見込みです。さらに、大学生世代の子供を持つ家庭を支援するための「特定親族特別控除」という新しい制度が創設される点も大きな変更点と言えるでしょう。
まずは、今回の改正で何がどう変わるのか、全体像を把握することが重要です。以下の表で主な変更点をまとめました。
| 項目 | 改正前(~令和6年分) | 改正後(令和7年分~) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得2,400万円以下で48万円 | 合計所得2,350万円以下で58万円に増額(低所得者層はさらに加算措置あり) |
| 給与所得控除 | 最低55万円 | 最低65万円に増額 |
| 扶養親族の所得要件 | 合計所得48万円以下 | 合計所得58万円以下に緩和 |
| 特定親族特別控除 | なし | 新設(19歳以上23歳未満の親族が対象) |
このように、多くの項目で控除額の引き上げや要件の緩和が行われます。詳細については、国税庁の公式サイトでも情報が公開されていますので、あわせて確認することをおすすめします。
(参照:国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)
扶養控除はいくらになるのか解説
今回の改正で「扶養控除の金額そのもの」が直接的に変わるわけではありません。しかし、扶養控除の対象となるための「所得要件」が緩和されるため、結果として控除を受けられる人が増える可能性があります。
扶養控除の対象になるかどうかは、扶養されている親族の年間の「合計所得金額」で決まります。この基準が、今回の改正の根幹である基礎控除の引き上げに伴い、変更されるのです。
扶養親族の所得要件の変更
これまで、配偶者や親族が扶養に入るための所得要件は「合計所得金額48万円以下」でした。これは給与収入のみの場合、年収103万円に相当し、「103万円の壁」の根拠の一つとなっていました。
令和7年分以降の所得税からは、この要件が「合計所得金額58万円以下」に引き上げられます。これは、給与収入のみであれば年収123万円に相当します。
ポイント
扶養に入れる年収の上限が、実質的に103万円から123万円に引き上げられると考えると分かりやすいでしょう(給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円)。
なお、扶養親族の年齢などに応じた控除額自体には変更はありません。例えば、一般の扶養親族であれば38万円、大学生世代である特定扶養親族であれば63万円の控除が受けられます。
高校生年代の扶養廃止はいつから?

「高校生年代(16歳~18歳)の子供に対する扶養控除が廃止される」という話を耳にしたことがあるかもしれません。これは、児童手当の拡充とセットで議論されているテーマです。
令和7年度税制改正では高校生年代の扶養控除(所得税38万円)の廃止や縮小は見送られました。そのため、2025年(令和7年)に行う年末調整や、2026年(令和8年)に行う確定申告において、この控除がなくなることはありません。
注意点
ただし、この議論が完全になくなったわけではありません。政府の資料では「令和8年度以降の税制改正で検討し、結論を得る」とされており、将来的に制度が変更される可能性は残っています。
過去には、中学生以下の子供に対する「年少扶養控除」が、子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴い廃止された経緯があります。今回も同様に、児童手当が高校生年代まで延長されたことを受け、税金と社会保障の役割分担を見直す観点から議論が続いています。今後の動向には注意が必要です。
配偶者控除は廃止される?
扶養控除とあわせてよく話題になるのが配偶者控除です。こちらも「廃止されるのでは?」という声が聞かれますが、今回の改正で配偶者控除および配偶者特別控除が廃止されることはありません。
むしろ、扶養控除と同様に所得要件が緩和され、より利用しやすくなります。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除:配偶者の合計所得が一定額以下の場合に受けられる控除。
配偶者特別控除:配偶者控除の対象外でも、配偶者の所得が一定額までであれば段階的に受けられる控除。
改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件は、扶養親族と同じく「合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下)」に引き上げられます。
さらに、配偶者特別控除で満額の38万円控除が受けられる年収の上限も、従来の150万円から160万円へと引き上げられます。これにより、パートタイマーとして働く配偶者が、これまでよりも気兼ねなく収入を増やせるようになることが期待されています。
特定親族特別控除の新設について
今回の改正で最も注目すべき点の一つが、「特定親族特別控除」の創設です。これは、主に大学生世代の子供(19歳以上23歳未満)がいる世帯を対象とした、全く新しい所得控除制度になります。
「子供がアルバイトで103万円を超えると扶養から外れて、世帯の手取りがガクッと減ってしまう…」そんな悩みを解消するための制度ですね。
これまでの制度では、子供のアルバイト収入が年収103万円を超えると、親は63万円の特定扶養控除を受けられなくなり、親の税負担が急激に増加するという問題がありました。このため、子供自身が年末になるとシフトを減らすといった「働き控え」が起こりがちでした。
新設される特定親族特別控除は、子供の合計所得金額が58万円を超えても、123万円以下である場合に、子供の所得に応じて親が段階的に控除を受けられる仕組みです。
控除額の仕組み
例えば、子供の合計所得金額が85万円以下(給与収入のみなら年収150万円以下)の場合、親はこれまで通り満額の63万円の控除を受けることができます。そして、子供の所得がそれを超えても、控除額がなだらかに減少していき、123万円(給与収入のみなら年収188万円)で控除額がゼロになります。これにより、世帯の手取りが急減する「崖」が解消されるのです。
2026年扶養控除の手続きと注意点

- 申告書の書き方と変更点
- 年末調整での留意事項
- 2026年扶養控除の対象者
- 住民税への影響も確認しよう
申告書の書き方と変更点
制度改正に伴い、年末調整で会社に提出する申告書の様式も変更されます。特に、これまで「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という名称だった書類が、さらに長くなります。
令和7年分からは、これに新設された控除の名称が加わり、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」となる予定です。一枚の紙に4つの申告書がまとまる形になり、記載する項目も増えるため、記入の際は注意が必要になります。
また、翌年(令和8年分)の給与から天引きする所得税額を決めるために提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も様式が変更されます。控除対象となる親族の範囲が変わるため、正しく記載できるよう事前に確認しておきましょう。
年末調整での留意事項
今回の改正は、令和7年(2025年)分の所得税から適用されます。したがって、会社員や公務員の方は、令和7年12月に行われる年末調整から新しいルールに基づいて税額が計算されることになります。
企業の人事・給与担当者と、従業員それぞれに留意すべき点があります。
企業担当者(源泉徴収義務者)の留意事項
企業側は、従業員に対して制度改正の内容を周知し、申告書を正しく提出してもらう必要があります。特に以下の点が重要です。
- 扶養親族の再確認:所得要件の緩和で、これまで対象外だった親族が新たに扶養に入れるケースがないか、従業員に確認を促す。
- 特定親族特別控除申告書の提出依頼:対象となる子供がいる従業員から、忘れずに申告書を提出してもらう。
- 新しい控除額での計算:改正後の基礎控除額や給与所得控除額を用いて、年末調整の計算を正確に行う。
従業員の留意事項
従業員側は、自身の家族状況を改めて確認し、必要な書類を会社に提出することが求められます。
- 家族の所得の確認:パートをしている配偶者やアルバイトをしている子供の年収見込み額を確認し、扶養に入れるかどうかを判断する。
- 申告書の正確な記入:様式が変更された申告書を、記入例などを参考に正しく記載して提出する。
2026年扶養控除の対象者

2026年に扶養控除の恩恵を受けられる対象者は、所得要件が「合計所得金額48万円以下」から「58万円以下」に緩和されることで、これまでよりも広がる可能性があります。
例えば、以下のようなケースでは、新たに扶養控除の対象となるかもしれません。
新たに扶養控除の対象になる可能性があるケース
ケース1:パート収入のある配偶者
これまでは年収103万円を超えないように調整していた方が、年収123万円まで働いても配偶者控除の対象になります。
ケース2:アルバイト収入のある子供(16歳以上)
子供のアルバイト年収が103万円を超えて123万円以下の場合でも、親は扶養控除(特定扶養親族の場合は63万円)を受けることができます。
前述の通り、この改正は令和7年分の所得税から適用されます。ご自身の家族が対象になるかどうか、この機会に必ず家族全員の所得状況を確認し、年末調整や確定申告に備えることが大切です。
住民税への影響も確認しよう
所得税の制度が変わると、住民税にも影響が及びます。ただし、注意すべきは適用されるタイミングに1年のズレがある点です。
所得税と住民税の適用時期の違い
所得税:令和7年分(2025年)から改正後の制度が適用されます。
住民税:令和8年度分(2026年度)から改正後の制度が適用されます。
これは、住民税が前年(1月1日~12月31日)の所得に基づいて計算される仕組みだからです。つまり、令和7年中の所得に対する住民税は、令和8年6月以降に納付することになるため、適用年度が一つ後ろにずれます。
今回の改正では、住民税の基礎控除なども所得税と同様に引き上げられます。これにより、住民税の非課税限度額も変わるため、これまで住民税が課税されていた方でも、非課税になるケースが出てくる可能性があります。
まとめ:2026年扶養控除の要点
- 2026年の扶養控除制度は廃止ではなく内容が大きく見直される
- 改正は令和7年分の所得税から適用開始
- 住民税への適用は1年遅れの令和8年度から
- 基礎控除は48万円から58万円に引き上げ
- 給与所得控除の最低額も55万円から65万円にアップ
- これにより扶養に入れる所得要件が合計所得58万円以下に緩和
- 給与収入のみなら年収123万円までが扶養の目安となる
- 配偶者控除の所得要件も同様に緩和される
- 配偶者特別控除が満額受けられる年収は160万円まで拡大
- 19歳以上23歳未満の子供を対象に特定親族特別控除が新設
- 子供の年収が123万円を超えても親の税負担が急増しなくなる
- 高校生年代の扶養控除は現時点では廃止も縮小もされない
- ただし将来的に見直される可能性は残っている
- 年末調整で提出する申告書の様式が変更され記載項目が増える
- 企業も従業員も制度変更を理解し正しく手続きを行う必要がある
・2026年の自動車規制はどう変わる?騒音・排ガス規制の要点
・2026年住宅ローン控除はどうなる?制度の今後と対策を解説

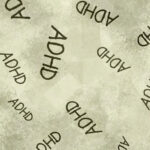
コメント