2026年の住宅ローン控除がどうなるのか、多くの方が気にかけているのではないでしょうか。
現行制度が2025年末で一区切りとなるため、2026年以降入居を検討している方にとっては大きな問題です。
制度の延長はあるのか、それともなくなるのか、廃止はいつからなのかという疑問や、住宅ローン控除が終わるとどうなるのかといった不安の声が知恵袋などでも多く見られます。
本記事では、最新の予想を基に、制度の今後がいつわかるのか、そしていつ決まるのかという見通しから、控除期間が13年なのか10年になるのか、5年目までといった期間の変更はあるのかという具体的なシミュレーションまで解説します。
<記事のポイント>
・2026年以降の制度は現在未定で見直しが予想される
・省エネ性能が今後の住宅ローン控除の重要な鍵を握る
・子育て世帯への優遇措置が継続されるかどうかが焦点
・正式な情報は2025年末の税制改正大綱で明らかになる
2026年住宅ローン控除の最新動向と今後の見通し

- 制度はなくなる?廃止はいつから?
- 延長の可能性と今後のどうなるかの予想
- 最新情報はいつわかる?いつ決まる?
- 住宅ローン控除が終わるとどうなるのか解説
- 2026年以降入居する場合の注意点
制度はなくなる?廃止はいつから?
結論から言うと、2026年以降に住宅ローン控除が完全に「なくなる」可能性は低いと考えられています。しかし、現行の制度は2025年12月31日までに入居した方を対象としており、それ以降の制度はまだ決まっていません。
住宅ローン控除は、これまで景気対策や住宅取得を促進するための重要な政策として、何度も内容の見直しや期間の延長が繰り返されてきました。このため、2026年以降も何らかの形で制度が存続する可能性は高いと言えるでしょう。
では、なぜ「廃止」や「なくなる」という不安の声が上がるのでしょうか。それは、近年の改正で制度が段階的に縮小されている傾向があるためです。
近年の主な制度変更点
- 控除率の引き下げ:かつて1%だった控除率が0.7%に引き下げられました。
- 借入限度額の縮小:住宅の性能に応じて設定される借入限度額が、一部引き下げられました。
- 省エネ基準の要件化:2024年以降、省エネ基準を満たさない新築住宅は原則として控除の対象外となりました。
このように、制度を利用するためのハードルが少しずつ上がっていることが、「廃止はいつから?」という懸念につながっているのです。
過去の制度改正の経緯
過去の経緯を振り返ると、住宅ローン控除が社会経済の状況に応じて柔軟に変化してきたことがわかります。以下の表は、近年の主な改正の歴史をまとめたものです。
| 改正年度 | 主な変更内容 | 背景・目的 |
|---|---|---|
| 2019年 | 消費税10%への増税に伴い、控除期間を10年から13年へ特例的に延長 | 消費増税による住宅購入の駆け込み需要とその反動減の緩和 |
| 2022年 | 控除率を1%から0.7%へ引き下げ。省エネ性能に応じた借入限度額を設定 | 支払利息を上回る控除(逆ザヤ)の是正、カーボンニュートラルへの貢献 |
| 2024年 | 省エネ基準を満たさない新築住宅を原則対象外に。子育て世帯等への優遇措置を導入 | 省エネ住宅の普及促進、子育て支援の強化 |
このように、政策目標に合わせて制度は常にアップデートされています。2026年以降の制度についても、これまでの流れを汲んだ内容になることが予想されます。
より詳細な情報や公式見解については、国土交通省のウェブサイトで確認することをおすすめします。
(参照:国土交通省 住宅ローン減税)
延長の可能性と今後のどうなるかの予想
多くの方が最も気にしている「制度は延長されるのか、どうなるのか」という点について、現在の情報から予想される今後の方向性を解説します。
前述の通り、制度が完全に廃止される可能性は低いものの、現行制度がそのまま延長されるわけではなく、内容が変更された上で延長されるというのが最も有力な見方です。
2026年以降に予想される主な変更点
- 省エネ性能要件のさらなる厳格化
- 控除率や控除期間の見直し
- 所得要件の変更
予想①:省エネ性能要件のさらなる厳格化
今後の住宅ローン控除を占う上で最も重要なキーワードが「省エネ」です。国は2050年のカーボンニュートラル実現に向け、住宅の省エネ化を強力に推進しています。
具体的には、2025年4月からすべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務付けられます。さらに政府は、「2030年までに新築される住宅について、ZEH(ゼッチ)水準の省エネ性能を確保することを目指す」という目標を掲げています。
この流れを受け、2026年以降の住宅ローン控除では、現在の省エネ基準よりもさらに高いレベル(例えばZEH水準)が最低要件となる可能性が十分に考えられます。一般住宅の控除額が縮小、あるいは対象外となる方向での見直しが進むかもしれません。
予想②:控除率や控除期間の見直し
現在の控除率0.7%や最大控除期間13年(新築の場合)についても、見直される可能性があります。国の財政状況や金利動向によっては、控除率がさらに引き下げられたり、省エネ性能が特に高い住宅以外は控除期間が10年に短縮されたりすることもシナリオとして考えられます。
予想③:所得要件の変更
現在、住宅ローン控除を受けられるのは合計所得金額が2,000万円以下の方です。この所得要件が、より低い金額に引き下げられる可能性もゼロではありません。公平性の観点から、より幅広い層への恩恵よりも、中所得者層への支援に重点が置かれる可能性も指摘されています。
このように、制度が存続したとしても、「どのような住宅を建てるか」によって受けられる恩恵が大きく変わる時代になっていくでしょう。今後の住宅選びでは、省エネ性能が資産価値にも直結する重要な要素となります。
最新情報はいつわかる?いつ決まる?

「結局、2026年以降の制度の詳細は、いつわかるの?」という疑問は当然のことです。住宅のような大きな買い物では、税制がどうなるかによって資金計画が大きく変わるため、一日でも早く情報を知りたいものです。
住宅ローン控除のような税制に関する正式な情報は、例年12月中旬に発表される「与党税制改正大綱」でその方向性が明らかになります。
つまり、2026年度の制度については、2025年(令和7年)の12月に、その全容がほぼ判明することになります。
情報が決定するまでの流れ
- 夏~秋ごろ:各省庁からの要望提出
国土交通省などが、財務省に対して来年度の税制改正に関する要望を提出します。この段階で、どのような見直しが検討されているのかがニュースなどで報じられることがあります。 - 12月中旬:与党税制改正大綱の決定
与党(自民党・公明党)が中心となって議論し、翌年度の税制改正の基本方針をまとめた「大綱」を発表します。ここで住宅ローン控除の具体的な内容(控除率、限度額、期間など)が盛り込まれます。この内容が、ほぼ最終決定となります。 - 翌年1月~3月:国会での審議・法案成立
大綱の内容に基づいた税制改正法案が国会に提出され、審議・可決されると、正式に法律として成立します。
したがって、住宅購入を検討している方は、2025年の年末のニュースに特に注意を払う必要があります。当ブログでも、最新情報が入り次第、速やかにお伝えしていく予定です。
情報収集でチェックすべき公式サイト
- 財務省:税制改正の概要
- 国土交通省:住宅ローン減税
- 官邸:首相官邸ウェブサイト
これらの公式サイトで一次情報を確認するのが最も確実です。
住宅ローン控除が終わるとどうなるのか解説
もし仮に、2026年以降に住宅ローン控除が延長されず「終わる」ことになった場合、私たちの家計にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは具体的な数字を用いて、そのインパクトを解説します。
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除される制度です。これがなくなるということは、その分の税負担が純増することを意味します。
シミュレーション:ローン残高3,000万円の場合
例えば、年末の住宅ローン残高が3,000万円あるケースで考えてみましょう。
控除額の計算:3,000万円 × 0.7% = 21万円
この場合、本来であれば最大で年間21万円の税金が還付または減額されます。制度がなくなると、この21万円をそのまま納税する必要が出てきます。
控除期間が10年間続くと仮定した場合、単純計算で最大210万円もの差が生まれる可能性があるのです。これは家計にとって非常に大きな影響と言わざるを得ません。
| 年末ローン残高 | 年間最大控除額(残高×0.7%) | 10年間の最大控除額合計 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 14万円 | 140万円 |
| 3,000万円 | 21万円 | 210万円 |
| 4,000万円 | 28万円 | 280万円 |
| 5,000万円 | 35万円 | 350万円 |
ご注意:上記の表はあくまで最大控除額の理論値です。実際に控除される額は、ご自身の所得税・住民税の納税額が上限となります。納税額が控除可能額より少ない場合は、納税額分までしか控除されません。
このように、住宅ローン控除の有無は、住宅購入後のキャッシュフローに直接的な影響を与えます。だからこそ、多くの方が制度の行方を注視しているのです。
金利の上昇局面では、この控除が利息負担を和らげる重要な役割も果たしているため、制度の動向はこれまで以上に重要性を増しています。
2026年以降入居する場合の注意点
2026年以降に入居を計画している方が、今から心に留めておくべき注意点をまとめました。制度が未定である現状では、いくつかのリスクを想定して計画を進めることが賢明です。
注意点①:現行制度が適用されないリスク
最も大きな注意点は、現行の有利な条件(借入限度額や控除期間など)が適用されない可能性があることです。
注文住宅の場合、契約から着工、竣工、そして入居までには1年以上の期間がかかることも珍しくありません。2025年中に契約したとしても、入居が2026年にずれ込んでしまうと、2026年からの新制度(まだ内容未定)が適用されることになります。
住宅ローン控除の適用条件は、原則として「契約日」ではなく「入居日」で判断されます。この点を誤解しないように注意が必要です。
もし2026年からの制度が現行よりも縮小された場合、想定していたよりも控除額が少なくなり、資金計画に狂いが生じる可能性があります。
注意点②:住宅の「性能」がより重要になる
前述の通り、今後の制度は「省エネ性能」の高い住宅を優遇する流れが加速すると予想されます。もし2026年以降に住宅を建てる、あるいは購入するのであれば、最低でも「省エネ基準適合住宅」以上の性能を持つ物件を選ぶことが、控除を受けるための必須条件になると考えておくべきでしょう。
性能の低い住宅を選んでしまうと、そもそも住宅ローン控除の対象外となってしまうリスクがあります。
注意点③:不確定要素を資金計画に織り込む
2026年以降に入居を計画する場合、住宅ローン控除による還付金を過度に期待した資金計画を立てるのは危険です。
私であれば、住宅ローン控除は「受けられたらラッキー」くらいの心構えで、控除がなくても無理なく返済できるようなローン計画を立てることをお勧めします。特に、繰り上げ返済の計画などを立てる際には、控除額が変動する可能性を考慮に入れると良いでしょう。
不確実な状況だからこそ、余裕を持った計画を立て、最新の情報を常にチェックする姿勢が大切になります。
2026年住宅ローン控除の具体的な影響と対策

- 子育て世帯への影響とシミュレーション
- ZEH証明書の重要性と取得方法
- 控除期間は13年か10年どっちを選ぶ?
- 5年目まで?10年以降の年末調整について
子育て世帯への影響とシミュレーション
2024年・2025年の制度では、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、借入限度額を上乗せする優遇措置が講じられています。2026年以降、この優遇措置がどうなるかは、特にお子様がいるご家庭や若いご夫婦にとって大きな関心事です。
現行の子育て世帯等への優遇措置とは?
まず、現在の優遇措置の内容を確認しましょう。「子育て世帯」とは19歳未満の扶養親族がいる世帯、「若者夫婦世帯」とは夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。
これらの世帯が2025年までに入居する場合、新築住宅の借入限度額が一般世帯に比べて上乗せされます。
| 住宅の種類 | 一般世帯の借入限度額 | 子育て・若者夫婦世帯の限度額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | +500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | +1,000万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | +1,000万円 |
この優遇があるかないかで、最大控除額も大きく変わってきます。
優遇措置の有無によるシミュレーション
例えば、ZEH水準省エネ住宅を購入した場合、13年間の最大控除額は以下のようになります。
- 一般世帯:3,500万円 × 0.7% × 13年 = 318.5万円
- 子育て世帯等:4,500万円 × 0.7% × 13年 = 409.5万円
その差は最大で91万円にもなり、これは無視できない金額です。
2026年以降も少子化対策は国の重要課題であるため、何らかの形で子育て支援策が継続される可能性は十分にあります。しかし、その規模や条件がどうなるかは不透明です。この優遇措置の適用を受けたいのであれば、2025年末までの入居を目指して計画を進めるのが最も確実な方法と言えるでしょう。
ZEH証明書の重要性と取得方法
今後の住宅ローン控除を語る上で欠かせないのが、ZEH(ゼッチ)をはじめとする省エネ性能を証明する書類です。2024年から省エネ基準を満たさない新築住宅が原則として控除の対象外となったことで、これらの証明書の重要性は飛躍的に高まりました。
なぜZEH証明書が重要なのか?
理由はシンプルで、より高い借入限度額と、それによる多額の税控除を受けるために必要不可欠だからです。前述の通り、住宅ローン控除の借入限度額は、住宅の省エネ性能に応じて明確にランク分けされています。
今後、制度がさらに省エネ重視になれば、「省エネ基準適合」は当たり前となり、「ZEH水準」やさらにその上の「長期優良住宅」の認定を受けているかどうかが、控除額の大きな分かれ目になる可能性があります。
これらの性能を証明するために、確定申告の際に「住宅省エネルギー性能証明書」や「建設住宅性能評価書」の写しなどを提出する必要があります。
証明書を発行できる機関
「住宅省エネルギー性能証明書」は、誰でも発行できるわけではありません。以下のいずれかの機関に依頼する必要があります。
- 登録住宅性能評価機関
- 登録建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
住宅の設計や施工を依頼するハウスメーカーや工務店に相談すれば、手続きを代行またはサポートしてくれる場合がほとんどです。建築計画の早い段階で、証明書の取得について確認しておきましょう。
証明書の発行には時間がかかる場合があるため、確定申告の時期に慌てないよう、早めの準備が肝心です。
詳細は、国土交通省の関連ページでご確認ください。
(参照:国土交通省 ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の証明書類について)
控除期間は13年か10年どっちを選ぶ?

現行制度では、住宅の種類や入居年によって控除期間が「13年」または「10年」に分かれています。どちらが適用されるかは、受けられる控除の総額に直結するため、非常に重要なポイントです。
控除期間の決まり方
基本的な考え方は以下の通りです。
- 新築住宅・買取再販住宅:原則13年
- 中古住宅(既存住宅):10年
ただし、新築住宅であっても、省エネ基準を満たしていない「その他の住宅」に該当する場合、控除期間は10年となります(2023年までに建築確認を受けた場合に限る。2024年以降の建築確認では対象外)。
以下の表に、住宅の種類ごとの控除期間と借入限度額(2024・2025年入居の一般世帯の場合)をまとめました。
| 住宅の種類 | 控除期間 | 借入限度額 | 13年間の最大控除総額 |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 13年 | 4,500万円 | 409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 13年 | 3,500万円 | 318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 13年 | 3,000万円 | 273万円 |
| その他の住宅(新築※) | 10年 | 2,000万円 | 140万円 |
| 中古住宅(省エネ基準以上) | 10年 | 3,000万円 | 210万円 |
| 中古住宅(その他) | 10年 | 2,000万円 | 140万円 |
※2023年末までに建築確認を受けた場合に限る
この表からわかるように、「13年」の控除を受けられるのは、省エネ性能の高い新築住宅または買取再販住宅に限られます。
「13年」を選ぶメリットと注意点
メリット:控除を受けられる期間が3年間延びるため、当然ながら控除総額は大きくなります。
注意点:11年目から13年目は、控除額の計算方法が「年末ローン残高の0.7%」か「建物購入価格の2%÷3」のいずれか低い方となる特例でした(消費増税時の措置)。現行制度では一律で「年末ローン残高の0.7%」ですが、将来の制度変更でこの部分が見直される可能性も念頭に置く必要があります。
2026年以降の制度でも、この「省エネ性能の高い住宅を長く優遇する」という傾向は続くと考えられます。住宅選びの際は、目先の価格だけでなく、控除期間を含めたトータルのメリットを考慮して判断することが重要です。
5年目まで?10年以降の年末調整について
住宅ローン控除の手続きについて、「控除は5年目までしかもらえないの?」「10年目以降はどうなるの?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるようです。ここでは、手続きの基本的な流れと、控除期間中の年末調整について解説します。
手続きの基本:初年度は確定申告、2年目以降は年末調整
まず、住宅ローン控除を受けるための手続きは、1年目と2年目以降で異なります。
- 1年目(入居した翌年):ご自身で確定申告を行う必要があります。会社員の方でも、この初年度だけは必須です。
- 2年目以降:会社員の場合、勤務先の年末調整で手続きが完了します。
「5年目まで」という特定の区切りはありません。控除が適用される期間(10年または13年)中は、毎年手続きを行うことで控除を受け続けることができます。
10年目以降の年末調整はどうする?
控除期間が13年の場合、当然10年目以降(11年目、12年目、13年目)も手続きが必要です。手続き方法は2年目から9年目までと変わりません。
2年目の確定申告が終わると、税務署から残りの控除期間分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類がまとめて送られてきます。(e-Taxで申告した場合は、ご自身で出力することも可能です。)
年末調整の際には、この申告書と、金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つを勤務先に提出します。
つまり、控除期間が13年であっても、10年目以降に特別な手続きが必要になるわけではありません。毎年忘れずに、必要書類を勤務先に提出すれば大丈夫です。
繰り上げ返済をした場合の注意
期間の途中で繰り上げ返済を行い、返済期間が当初の契約から10年未満になった場合、その時点で住宅ローン控除の対象外となってしまいます。繰り上げ返済を検討する際は、返済期間が10年未満にならないように注意しましょう。
2026年住宅ローン控除の情報を確認しよう
この記事では、2026年の住宅ローン控除がどうなるのか、その見通しと対策について解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。
- 2026年以降の住宅ローン控除制度はまだ未定
- 現行制度は2025年12月31日の入居までが対象
- 制度が完全になくなる可能性は低いが内容の縮小が予想される
- 今後の制度では省エネ性能がより一層重要な要件となる見込み
- ZEH水準省エネ住宅など高い性能の住宅が優遇される流れは継続する可能性が高い
- 省エネ性能を証明するZEH証明書などの書類が必須になる
- 2026年以降の制度の詳細は2025年12月頃の税制改正大綱で判明する
- 正式決定は与党税制改正大綱の内容がほぼ反映される
- 情報収集は国土交通省や財務省の公式サイトが確実
- 子育て世帯への優遇措置が2026年以降も続くかが焦点
- 控除期間は省エネ性能の高い新築で13年、中古住宅は10年が基本
- 手続きは初年度が確定申告で2年目以降は年末調整
- 繰り上げ返済で返済期間が10年未満になると控除対象外になるので注意
- 控除はまず所得税から行われ、引ききれない分は上限付きで住民税から控除される
- 2026年以降に入居を計画する場合は制度の不確実性を考慮した資金計画が重要
・2026年法改正一覧|会社と暮らしに関わる重要ポイント
・2026年最低賃金予想を深掘り!主要都市の動向と今後の見通し

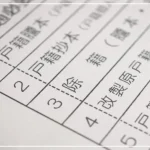
コメント