2027年の大学受験を控える皆さん、共通テストの日程は気になりますよね。
この記事では、2027年の大学入試日程の全体像から、具体的な共通テスト時間割、さらには2027年共通テストの科目詳細まで、受験生が知りたい情報を解説します。
<記事のポイント>
・2027年共通テストの正確な日程
・出願方法や試験科目などの詳細
・2028年の共通テストに関する情報
・志望校選びに役立つヒントを得られる
2027年共通テストの日程

- 2027年大学入試日程の全体像
- 発表された共通テスト時間割
- 2027年共通テスト科目の詳細
- 共通テスト出願方法の注意点
- 本試験と追試験の具体的な日程
2027年大学入試日程の全体像
2027年度の大学入学者選抜における中心的なイベントである大学入学共通テストの日程が、大学入試センターより正式に発表されました。受験生にとっては、この日程を軸に学習計画を立てることが極めて重要になります。
まず結論として、2027年(令和9年)の共通テスト本試験は、1月16日(土)と17日(日)の2日間で実施されます。これは例年通り「1月の第3土曜日および日曜日」という原則に沿った日程です。
この共通テストを皮切りに、本格的な大学入試シーズンが始まります。国公立大学の個別学力検査(2次試験)の日程も発表されており、前期日程は2027年2月25日(水)から、後期日程は3月12日(金)以降に各大学で実施される予定です。一部の公立大学では中期日程が設定される場合もあります。
私立大学の入試日程は大学ごとに多様ですが、一般的には共通テスト利用入試の出願が年明けから始まり、独自の個別試験は1月下旬から2月にかけてピークを迎えます。
総合型選抜や学校推薦型選抜は、これより早い時期に行われるため、該当する受験生は別途スケジュールを確認する必要があります。
入試スケジュールの要点
- 共通テスト本試験:2027年1月16日(土)・17日(日)
- 国公立大学2次試験(前期):2027年2月25日(水)~
- 国公立大学2次試験(後期):2027年3月12日(金)~
- 私立大学一般選抜:1月下旬~2月が中心
>>大学入試センターで確認する
このように、共通テストの日程を把握することは、その後の国公立大学や私立大学の入試スケジュールを見通し、戦略的に出願計画を立てるための第一歩と言えるでしょう。
発表された共通テスト時間割
2027年共通テストの具体的な時間割は、受験生が当日のシミュレーションを行い、時間配分の戦略を練る上で不可欠な情報です。大学入試センターから公表された2日間の詳細なスケジュールを確認しましょう。
時間割は、1日目に文系科目、2日目に理系科目が中心に配置される構成となっています。特に、地理歴史・公民や理科②では、2科目を選択する場合の解答時間に注意が必要です。
| 試験教科・科目 | 試験時間 | |
|---|---|---|
| 第1日(1月16日) | 地理歴史・公民 | 9:30 ~ 11:40(2科目選択) 9:30 ~ 10:30(1科目選択) |
| 国語 | 13:00 ~ 14:30(90分) | |
| 外国語(リーディング) | 15:20 ~ 16:40(80分) | |
| 第2日(1月17日) | 理科① | 9:30 ~ 10:30(60分) |
| 数学① | 11:20 ~ 12:30(70分) | |
| 数学② | 13:50 ~ 15:00(70分) | |
| 理科② | 15:50 ~ 18:00(2科目選択) 15:50 ~ 16:50(1科目選択) |
科目選択と試験時間に関する注意
地理歴史・公民と理科②で2科目を選択する場合、第1解答科目と第2解答科目の間に答案回収などの時間を含め、合計130分の試験時間が設定されています。実際の解答時間は各60分、合計120分です。
時間配分を誤らないよう、過去問題などで十分に練習しておくことが大切です。
また、外国語のリスニングはリーディング試験の後に行われます。ICプレーヤーの操作確認時間なども含まれるため、全体の所要時間を把握しておきましょう。
2027年共通テスト科目の詳細
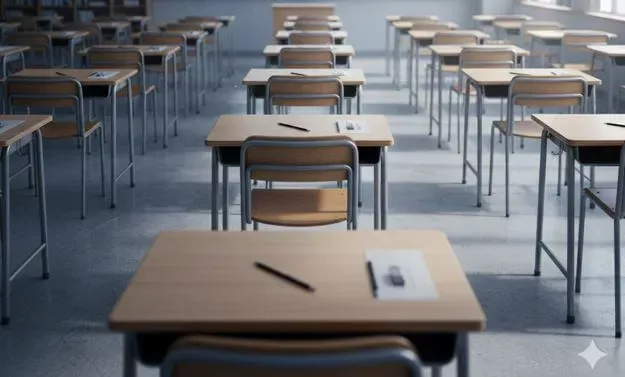
2027年度の共通テストは、高等学校の新学習指導要領に対応した入試となるため、出題科目にいくつかの重要な変更点があります。特に、新教科「情報」が追加される点は、すべての受験生が把握しておくべき最大のポイントです。
各教科の科目構成は以下の通りです。
出題教科・科目一覧
- 国語:『国語』1科目のみ。「近代以降の文章」「古典(古文・漢文)」から出題されます。試験時間は90分に変更されています。
- 地理歴史・公民:『地理総合/地理探究』、『歴史総合/日本史探究』、『歴史総合/世界史探究』、『公共/倫理』、『公共/政治・経済』、『地理総合、歴史総合、公共』(うち2科目を選択解答)から最大2科目選択。
- 数学:『数学Ⅰ,数学A』と『数学Ⅱ,数学B,数学C』の2科目。
- 理科:『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』(基礎を付した科目)と、『物理』『化学』『生物』『地学』(基礎を付さない科目)から選択。
- 外国語:『英語』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』から1科目選択。『英語』はリーディングとリスニングで構成されます。
- 情報:『情報Ⅰ』が新設され、原則として必須科目となります。
「情報Ⅰ」への対策
新たに導入される「情報Ⅰ」は、プログラミングやデータの活用、情報セキュリティなど、現代社会に必須の知識を問う科目です。
多くの国公立大学で必須科目とされる見込みであり、早期からの対策が合格の鍵を握ります。学校の授業を大切にするとともに、参考書や問題集を活用して演習を重ねましょう。
志望する大学がどの科目を選択方式として課すのか、配点はどうなるのかを事前に大学のウェブサイトや募集要項で確認し、受験科目を見極めることが重要です。特に地歴公民の選択パターンは複雑なため、自分の受験に必要な科目を間違えないように注意してください。
共通テスト出願方法の注意点
2027年度の大学入学共通テストから、出願手続きが大きく変更されます。これまでの紙の願書による郵送出願が廃止され、完全にWeb出願へと移行する点が最大の注意点です。
主な流れは、「出願サイトでの情報登録」と「検定料の支払い」の2ステップです。それぞれの期間が異なるため、スケジュールを正確に把握しておく必要があります。
出願登録には、氏名や住所などの基本情報に加え、顔写真データのアップロードが必要になります。事前にスマートフォンやデジタルカメラで撮影した適切なデータを用意しておきましょう。また、検定料はクレジットカード、コンビニ払い、金融機関ATM(ペイジー)などで支払うことができます。
出願時の重要チェックポイント
- 期間の厳守:登録期間と支払い期間は最終日時が異なります。どちらか一方でも期限を過ぎると出願できなくなるため、余裕を持った手続きを心がけましょう。
- 受験上の配慮:病気や障害等により受験上の配慮が必要な場合は、Web出願とは別に事前の申請が必要です。申請期間は出願期間よりも早く設定されているため、該当する方は大学入試センターの「受験上の配慮案内」を必ず確認してください。
- 入力情報の確認:登録内容に誤りがないか、送信前に何度も確認することが大切です。特に、受験する教科や科目の選択ミスは致命的になりかねません。
初めてのWeb出願で戸惑うこともあるかもしれませんが、大学入試センターのウェブサイトで詳細なマニュアルが公開されます。手順を一つひとつ確認しながら、落ち着いて手続きを進めましょう。
本試験と追試験の具体的な日程
大学入学共通テストでは、やむを得ない事情で本試験を受験できなかった志願者のために、追試験の機会が設けられています。万が一の事態に備え、追試験の日程と対象となる条件を理解しておくことも大切です。
結論から言うと、2027年度の共通テストにおける本試験と追試験の日程は以下の通りです。
試験日程のまとめ
- 本試験:2027年1月16日(土)、17日(日)
- 追試験:2027年1月24日(土)、25日(日)
追試験は、本試験の1週間後に実施されます。試験会場は各都道府県に1〜2箇所程度設けられるのが通例です。
追試験の受験が許可されるのは、病気や負傷、あるいは避けられない事故(交通機関の遅延や災害など)といった、本人の責めに帰すことのできない理由により、本試験の全科目または一部の科目を受験できなかった場合に限られます。
例えば、「寝坊した」「勉強が間に合わなかった」といった自己都合の理由は認められません。
追試験の申請手続き
追試験を受験するためには、本試験当日に試験場の担当者へ申し出た上で、後日、医師の診断書などの証明書類を提出する正式な手続きが必要です。手続きの詳細は、試験当日に指示がありますので、まずは落ち着いて試験場の係員に相談することが重要です。
もちろん、全ての受験生が万全の体調で本試験に臨めることが一番です。試験日に向けて、学習面だけでなく、健康管理にも最大限の注意を払いましょう。
2027年共通テストの日程と併せて知りたい情報

- 2028年共通テスト日程の予測
- 役立つ2028年共通テストカウントダウン
- 共テ6割でいける大学の探し方
- 最新情報を入手する方法
2028年共通テスト日程の予測
高校2年生以下の皆さんにとっては、自身が受験する2028年度以降の共通テスト日程も気になるところでしょう。まだ公式発表はありませんが、これまでの慣例から日程を高い精度で予測することが可能です。
共通テスト(およびその前身のセンター試験)は、「1月の第3土曜日とその翌日の日曜日」に実施されるのが長年のルールとなっています。このルールを2028年のカレンダーに当てはめてみましょう。
2028年1月の第3土曜日は15日です。したがって、このルールが変更されない限り、2028年度の共通テストは1月14日(土)と15日(日)に実施される可能性が高いと言えます。
あくまで「予測」である点に注意
この日程は、過去の傾向に基づく予測であり、確定情報ではありません。自然災害や社会情勢の大きな変化など、不測の事態によって日程が変更される可能性もゼロではありません。
最終的な確定情報は、受験年度の前年6月頃に文部科学省および大学入試センターから公式に発表されます。必ず公式サイトで確認するようにしてください。
とは言え、この予測日を一つの目標として設定することで、長期的な学習計画を立てやすくなります。高校1年生や2年生の段階から、この日程を意識して日々の学習に取り組むことは、現役合格への大きなアドバンテージとなるでしょう。
役立つ2028年共通テストカウントダウン
長期にわたる大学受験の勉強では、モチベーションを維持し続けることが非常に重要です。そこで役立つのが、試験本番までの残り時間を視覚的に示してくれる「カウントダウンツール」の活用です。
2028年の共通テスト日程を先ほど「1月14日・15日」と予測しました。この日をゴールに設定し、カウントダウンを開始することで、日々の学習に張り合いが生まれます。
具体的には、以下のようなツールが考えられます。
- Webサイトのカウントダウンタイマー:受験情報サイトや個人が作成したタイマーサイトなど、検索すれば多くのサービスが見つかります。パソコンのブックマークに登録しておくと良いでしょう。
- スマートフォンのアプリ:カウントダウン専用のアプリをインストールすれば、ホーム画面のウィジェットに設定して常に残り日数を確認できます。学習記録機能が付いたアプリもおすすめです。
- 手作りの日めくりカレンダー:アナログな方法ですが、毎日自分の手でカレンダーをめくることで、一日一日を大切にする意識が高まります。
ただ残り日数を見て焦るのではなく、「あと〇〇日だから、今週はこの単元を終わらせよう」というように、具体的な行動計画と結びつけることが大切です。カウントダウンを、自分を追い込むための道具ではなく、計画的に学習を進めるためのパートナーとして活用しましょう。
友達と一緒に同じカウントダウンツールを使い、お互いの進捗を報告し合うのも、モチベーション維持に効果的かもしれません。
共テ6割でいける大学の探し方

共通テストの目標スコアを設定することは、具体的な学習計画を立てる上で非常に有効です。特に「共通テストで6割の得点率」というのは、多くの受験生にとって一つの目安となるラインでしょう。では、実際に得点率60%前後で出願可能な大学はどのように探せばよいのでしょうか。
最も効率的な方法は、大手予備校や進学情報サイトが提供するデータベースを活用することです。
例えば、以下のようなウェブサイトが有名です。
- パスナビ(旺文社)
- スタディサプリ進路(リクルート)
- 河合塾 Kei-Net
- 東進ドットコム
これらのサイトでは、「共通テスト利用入試」を実施している大学を、学部系統や地域、そして「共通テストのボーダー得点率」で絞り込んで検索することができます。検索フィルターで得点率を「55%~65%」のように設定すれば、目標とする大学群をリストアップすることが可能です。
検索結果を利用する際の注意点
ボーダー得点率は、あくまで前年度入試の結果に基づく目安であり、その年の合格を保証するものではありません。また、大学によっては共通テストの配点比率が低く、個別試験(2次試験)の成績が重視される場合も多くあります。
共通テストの得点率だけで安易に志望校を決定するのではなく、必ず個別試験の科目や配点、過去の入試問題なども含めて総合的に判断することが重要です。
まずは自分の興味のある学問分野や、通学可能な範囲の大学をいくつかピックアップし、それらの大学のボーダー得点率を調べてみることから始めましょう。具体的な目標が見えることで、学習への意欲も一層高まるはずです。
最新情報を入手する方法
大学入試に関する情報は、日々更新される可能性があります。特に、試験の日程や出題範囲、選抜方法といった重要な事柄については、常に最新かつ正確な情報を入手することが不可欠です。誤った情報や古い情報に惑わされないために、信頼できる情報源を把握しておきましょう。
結論として、最も信頼性が高く、全ての情報の基本となるのは「大学入試センター」の公式ウェブサイトです。
最重要情報源:大学入試センター
共通テストに関する実施要項、出題方針、Q&A、Web出願の手引きなど、全ての公式情報は大学入試センターで発表されます。受験生は必ず定期的にチェックする習慣をつけましょう。
大学入試センターの他にも、以下の情報源を併せて活用することをおすすめします。
- 文部科学省のウェブサイト:大学入学者選抜全体の大きな方針や大綱が発表されます。
- 各大学の公式ウェブサイト:個別試験の日程や募集要項、アドミッション・ポリシーなど、大学ごとの詳細な情報が掲載されています。志望校のサイトはこまめに確認しましょう。
- 在籍する高等学校:進路指導の先生方は、最新の入試情報に精通しています。定期的な面談などを通じて、積極的に相談しましょう。
- 大手予備校や進学情報サイト:入試分析や模試の結果データなど、受験戦略を立てる上で有益な情報を提供しています。ただし、あくまで二次的な情報源として活用し、最終的には必ず公式サイトで裏付けを取ることが大切です。
特にSNSなどでは不確かな情報が拡散されることもあります。一つの情報を鵜呑みにせず、必ず公式情報源でファクトチェックを行う冷静さを持ちましょう。
2027年の共通テスト日程の最終確認
この記事では、2027年度大学入学共通テストの日程を中心に、科目や出願方法、関連情報について詳しく解説してきました。最後に、記事全体の要点をリスト形式でまとめ、最終確認としましょう。
- 2027年共通テストの本試験は1月16日と17日
- 追試験は1月24日と25日に実施される
- 国立大学の二次試験前期日程は2月25日から
- 出願はWeb出願に完全移行する
- 出願登録期間と検定料支払い期間は異なるため注意が必要
- 新課程に対応し「情報Ⅰ」が必須科目に加わる
- 国語の試験時間は90分に変更される
- 数学は数学①と数学②に分かれる
- 地歴公民の科目選択パターンは複雑なため要確認
- 英語リスニングの配点も重要になる
- 2028年の共通テストは1月14日と15日と予測される
- 最新情報は必ず大学入試センター公式サイトで確認する
- 共テ6割の大学は進学情報サイトで検索可能
- 得点率だけでなく個別試験の配点も考慮して志望校を選ぶ
- 学習計画にはカウントダウンツールの活用がおすすめ


コメント